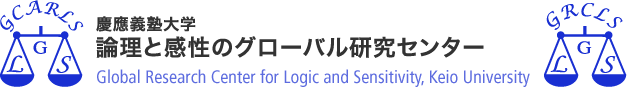論理と感性のグローバル研究センター メンバー紹介 Introducing the members of our Center
専任教員University's tenured members

- 眞島 裕樹(ましま ゆうき) Mashina, Yuki
- 慶應義塾大学医学部 助教
-
精神医学、身体症状症
名誉教授メンバーProfessor emeritus
- 宮坂 敬造(みやさか けいぞう) Miyasaka, Keizou
慶應義塾大学 文学部 名誉教授
文化人類学(象徴人類学、心理と感覚人類学、医療人類学、映像人類学、精神生態の人類学)
- 岡田 光弘(おかだ みつひろ) Okada, Mitsuhiro
慶應義塾大学 文学部 名誉教授・初代センター長(2014-2019年度)
-
論理学・哲学・論理思考研究・論理推論の認知科学と心理学・情報科学及び計算機科学の論理、アルゴリズム環境の倫理
有期教員及び研究員Project-assistant professors and project-researchers
- 秋吉 亮太(あきよし りょうた) Akiyoshi, Ryota
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
数学・論理学の哲学、数理論理学(証明論)、理論計算機科学(タイプ理論)、ロボット倫理、スマートシティ
- 徐 鳴鏑(じょ めいてき) Xu, Mingdi
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
コミュニケーション機能の発達
- 白野 陽子(はくの ようこ) Hakuno, Yoko
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
社会性の発達
- 秦 政寛(はた まさひろ) Hata, Masahiro
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
言語獲得
- 星野 英一(ほしの えいいち) Hoshino, Eiichi
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
視覚記憶・認知機能に関わる脳機能
- 森本 智志(もりもと さとし) Morimoto, Satoshi
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
計算論的神経科学、音楽認知科学、データ駆動型科学
- 小笠原 忍(おがさわら しのぶ) Ogasawara, Shinobu
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
臨床心理学、応用行動分析学
- 品川 和志(しながわ かずし) Shinagawa, Kazushi
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
マインドワンダリング、注意、脳波、fMRI
- 周 一禎(しゅう いってい) Shu, Ittei
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
多感覚知覚、心理物理学
- 天本 貴之(あまもと たかゆき) Amamoto, Takayuki
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
言語哲学、形式意味論、語用論
- 狩野 祐人(かのう ゆうと) Kano, Yuto
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
医療人類学、地域精神医療
- 瀬口 瑛子(せぐち あきこ) Seguchi, Akiko
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
動物心理学・行動神経内分泌学
- 船蔵 颯(ふなくら はやて) Funakura, Hayate
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
計算言語学
- 青田 伊莉安(あおた いりあ) Aota, Illia
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
動物心理学、行動神経内分泌学
- 鈴木 彩香(すずき あやか) Suzuki, Ayaka
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
日本語文法、統語論、意味論、テンス、アスペクト
- 田仲 祐登(たなか ゆうと) Tanaka, Yuto
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
生理心理学・認知神経科学・内受容感覚・感情
- 辻 幸樹(つじ こうき) Tsuji, Koki
- 慶應義塾大学 KGRI 研究員
認知神経科学、実験心理学
共同研究員Collaborative researchers
- 朝比奈 正人(あさひな まさと) Asahina, Masato
神経内科学、神経科学、自律神経系
- 池田 功毅(いけだ こうき) Ikeda, Koki
心理学の再現性、ディープニューラルネットワーク
- 石川 菜津美(いしかわ なつみ) Ishikawa, Natsumi
臨床発達心理学、応用行動分析学
- 石塚 祐香(いしづか ゆうか) Ishizuka, Yuka
臨床発達心理学、応用行動分析学
- 井出野 尚(いでの たかし) Ideno, Takashi
社会心理学、消費者行動、行動意思決定論
- 牛山 美穂(うしやま みほ) Ushiyama, Miho
文化人類学、医療人類学
- 大前 美由希(おおまえ みゆき) Ohmae, Miyuki
20世紀アメリカ美術、現代彫刻
- 小野 智恵(おの ともえ) Ono, Tomoe
-
美学、映画学
- 窪田 愛(くぼた あい) Kubota, Ai
形式意味論、日本語
- 小泉 篤士(こいずみ あつし) Koizumi, Atsushi
-
古代ギリシャ・ローマ美術史
- 佐藤 有理(さとう ゆうり) Sato, Yuri
-
認知科学、論理学、意味論、視覚表現
- 佐野 貴紀(さの たかのり) Sano, Takanori
-
実験心理学、意思決定、眼球運動
- 柴田 みどり(しばた みどり) Shibata, Midori
-
認知神経科学、語用論
- 高橋 優太(たかはし ゆうた) Takahashi, Yuta
-
論理学の哲学、論理学
- 津田 裕之(つだ ひろゆき) Tsuda, Hiroyuki
- 慶應義塾大学 KGRI 特任助教
認知心理学
- 時田 真美乃(ときた まみの) Tokita, Mamno
認知科学、進化心理学、心の理論、再帰的思考、協調学習
- 直井 望(なおい のぞみ) Naoi, Nozomi
発達心理学・神経科学、発達障害の機序の解明および早期介入の効果についての行動・神経学的検討
- 長田 有里子(ながた ゆりこ) Nagata, Yuriko
応用行動分析、発達障がい、自閉スペクトラム症、自然発達行動支援
- 野地 洋介(のじ ようすけ) Noji, Yosuke
医療人類学
- 福田 恭子(ふくだ きょうこ) Fukuda, Kyoko
美術史、風景画、ニコラ・プッサン
- 星 聖子(ほし せいこ) Hoshi, Seiko
-
西洋美術史、イタリア・ルネサンス、ヴェネツィア・ルネサンス、祭壇画研究
- 星川 美紀(ほしかわ みき) Hoshikawa, Mkiki
ヒューマンロボットインタラクション、認知科学
- 森井 真広(もりい まさひろ) Morii, Masahiro
実験心理学、意思決定、眼球運動測定
- 山田 理恵(やまだ りえ) Yamada, Rie
社会学
- 山根 千明(やまね ちあき) Yamane, Chiaki
-
20世紀西洋美術(ドイツ)、美術と知覚理論、色彩論史
- 劉 璐(りゅう ろ) Ryu, Ro
-
死の社会学
- Barry v. Rolett Barry v. Rolett
-
考古学、文化人類学、環境科学、太平洋島嶼研究、ポリネシア研究、南東中国研究